 ニュース
ニュース 広島のカキ大量死問題:瀬戸内海養殖業の危機
なぜ“カキ大量死”が起きているのか2025年秋以降、広島県内を中心に、養殖カキの“へい死”(大量死)が相次いで報告されています。県の報告では、被害は「県内のほぼ全海域」に広がっており、場所によっては 8〜9割のカキが死滅した 海域もあるとさ...
 ニュース
ニュース  ニュース
ニュース 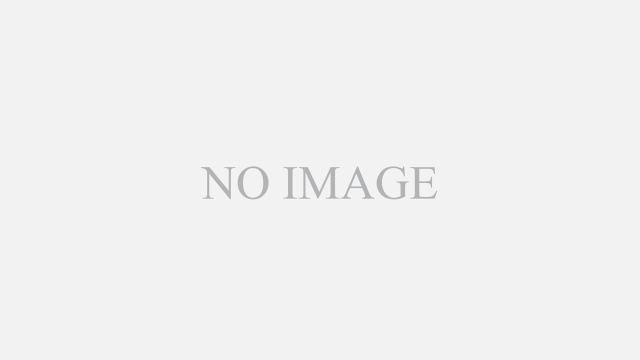 ニュース
ニュース 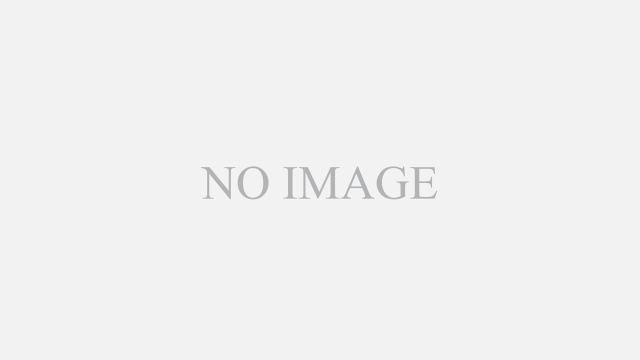 ニュース
ニュース  ニュース
ニュース  ニュース
ニュース  ニュース
ニュース 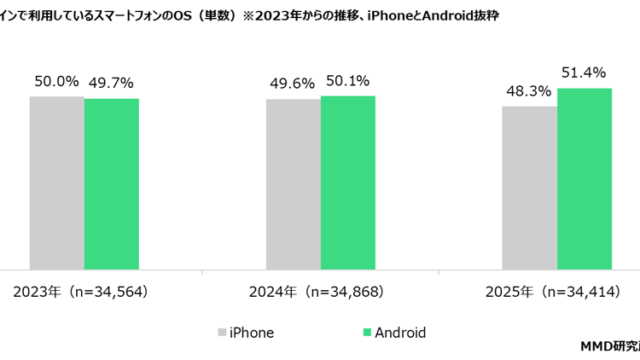 ニュース
ニュース 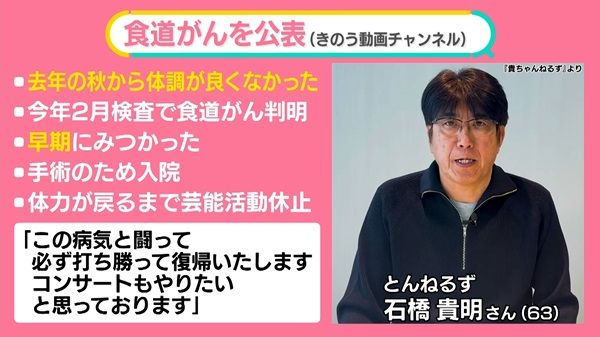 ニュース
ニュース 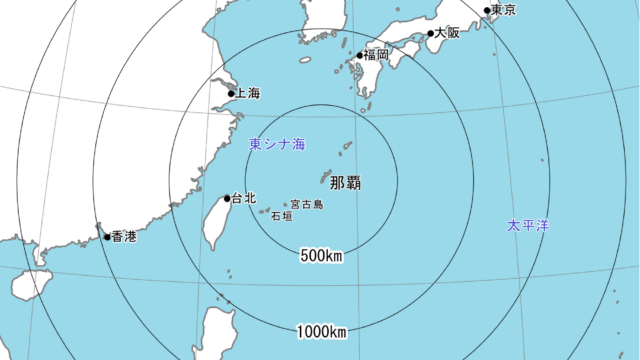 ニュース
ニュース